ビースターズの打ち切り理由について気になって検索された方に向けて、この記事では物語の核心や未回収の伏線、そして作品にまつわる数々の謎を総合的に解説します。
ビースターズの最終回がなぜあっさりとした印象になったのか、アニメがどこまで描かれたのか、そしてレゴシとハルの子供が登場しなかった理由などについて、原作漫画とアニメの違いや読者の疑問に答える形で丁寧に掘り下げていきます。
また、ビースターズのメロン死亡の真相やジュノ死亡の噂、さらには登場キャラの中で重要な意味を持った死亡キャラたちについても詳しく解説します。
ビースターズが気持ち悪いと感じる読者がいる理由や、作品世界の中で描かれた恋愛と暴力、本能と理性のせめぎ合いに対する考察も含め、読み応えのある内容をお届けします。
レゴシの死亡説や続編の可能性、さらには作者が意図的に描かなかったとされる博愛の食肉というエピソードの意味についても追及しています。
ネット掲示板で語られたビースターズの展開やネタバレの影響、そして作者の創作スタンスがどのように物語に影響したのかについても、考察を交えながら分かりやすく説明しています。
ビースターズのwikiなどでは触れられていないような裏側の事情や深い読み解きを求める方にとって、この記事は充実した情報源となるはずです。
アニメ版の最終回がどこまで放送されたのか、また全巻を読んだ上で浮かぶ謎や疑問に応える形で構成されており、初めてビースターズに触れる方からコアなファンまで楽しめる内容になっています。
作品に隠された真意やメッセージを考察することで、改めてビースターズという物語の魅力を再発見していただければ幸いです。
ビースターズの打ち切り理由を徹底解説|物語の謎と結末の真相とは?
-
ビースターズ 打ち切り 理由は「博愛の食肉」が描かれなかったから?
-
ビースターズ メロン 死亡の真実とは?未描写の重要シーンを考察
-
ビースターズ 気持ち悪いと感じる理由は世界観かキャラ設定か?
-
ビースターズ 死亡キャラ一覧とその意義を振り返る
-
ビースターズ レゴシ ハル 子供の描写がない理由とその意味
-
ビースターズ 最終回があっさりだった理由と読者の反応
打ち切り理由は「博愛の食肉」が描かれなかったから?
ビースターズの打ち切りをめぐる最大の焦点は、「博愛の食肉」と呼ばれる重要なエピソードが漫画本編で描かれなかったことにあります。
これは、物語全体のテーマと重なる極めて重要な要素でありながら、連載終了まで一切触れられることがありませんでした。なぜそのような核心部分が省略されたのか、多くの読者が疑問を抱き、打ち切りのような形で終わったと受け止めたのです。
「博愛の食肉」とは、草食動物であるハルが肉食のメロンに自らを「食べてもいい」と提案することで成立する、肉食・草食間の究極の信頼と平等を示す象徴的な出来事です。これは、作中で語られる「愛の食肉」「友情の食肉」に続く第三の形として想定され、作者・板垣巴留が描こうとしていた可能性が高い内容です。
このエピソードの核心は、メロンがハルを愛したがゆえに食べたいという衝動に駆られながらも、愛のゆえに食べられなかったという葛藤と自己犠牲にあります。作者が意図していたかは明言されていませんが、第166話の「奇魂祭」でのハルとメロンのやりとりが、この「約束」を暗示していたと読み解くファンもいます。
一方で、この話をネット掲示板(5ちゃんねる)に書き込んでいた一部の読者が先読みしてしまったため、作者が意図的に描かなかったのではないかという見方も存在します。実際、作者が「嫌いなものはインターネット」と雑誌のコメントで明言していたことや、過去に父・板垣恵介も展開を読者の推察によって変更したという噂が根拠として語られています。
結果として、物語の最も重要で象徴的なテーマが描かれなかったことで、多くの伏線が未回収のまま残り、最終回もあっさりとした印象になってしまいました。このことが読者の間で「ビースターズは打ち切りになったのでは?」と捉えられる一因となっています。
メロンの死亡の真実とは?未描写の重要シーンを考察
ビースターズの終盤における最大の謎の一つは、混血の主要キャラクター・メロンの死の真相です。彼がどうして死亡したのか、作中では明確に描写されておらず、読者の間で多くの考察と憶測が飛び交っています。
この「未描写」が意味するのは、作者があえて物語の中で語らなかった、あるいは語れなかった重要な背景が存在するということです。とくに注目されているのは、メロンとハルの間で交わされた「自分を食べてもいい」という約束と、それに基づく行動の顛末です。
メロンは、肉食と草食、混血という存在への差別を嫌い、誰からも平等に扱われる社会を強く望んでいました。そんな彼が、何の見返りも期待せず、自分を「普通の獣」として接してくれたハルに心を奪われるのは自然な流れでした。そして、その感情が「愛」と「食欲」が同時に発生するこの世界特有のメカニズムを刺激したのです。
結果的に、メロンはハルを食べようとする衝動にかられますが、寸前で踏みとどまり、ハルの命を守ろうとしたことから、自らの死を選んだと考えられます。これは作中では明言されていないものの、作者の過去作品『BEAST COMPLEX』に見られる「共食いに愛を込める」というテーマともつながる要素です。
メロンの自殺という結末は、漫画では描かれず、物語がレゴシとルイの視点で「世界が変わった」と表現されることでぼかされました。読者の間では、「メロンとハルの関係」が世界を変えた出来事であり、それを無理に書き換えたために、多くの矛盾や未回収が残ったという解釈が有力です。
最終的にメロンは、ハルの記憶を失いながらも、彼女から受け取った幸福感だけを胸に独房で笑顔を浮かべているというラストカットが提示されます。
この描写こそ、彼が「愛を知り、守るために死を選んだ」という真実を象徴していると考えられています。物語の大団円に繋がる最も大切な要素でありながら、読者の想像に委ねられたことで、かえって深い余韻を残したといえるでしょう。
気持ち悪いと感じる理由は世界観かキャラ設定か?
ビースターズを「気持ち悪い」と感じる読者や視聴者がいるのは、その独特な世界観とキャラクターの設定に起因しています。
この作品では、動物が擬人化されて人間のように生活している一方で、肉食と草食の本能的な葛藤や恋愛、食欲など、極めて生々しいテーマがリアルに描かれているからです。
たとえば、レゴシというオオカミが草食のウサギ・ハルに恋をしながらも、「食べたい」という衝動と戦う描写は非常に独特です。このような愛と捕食欲の交錯が、人間社会に置き換えるときわめてセンシティブに映るため、「気持ち悪い」と感じる人が出てくるのも無理はありません。
また、ハルの性格や行動も、特に一部読者からは理解されにくく、「不思議ちゃん」や「支離滅裂」と形容されることもあります。小動物的な可愛らしさとは裏腹に、彼女が持つ奔放さや自己犠牲的な思考は、読者に強い違和感を与えることがあります。
さらに、物語全体に流れる「被捕食者の本能」や「生命動物と自然動物」といった概念も複雑で、理解が追いつかないまま話が進行するため、混乱や不快感を覚える原因となります。拳銃の存在や裏市の描写など、世界観の整合性に疑問が残る点も一因です。
総じて言えば、「気持ち悪い」と感じるのは、設定そのものではなく、その設定をどう描写し、どんな感情に読者をさらすかという点にあるのです。動物たちの本能と理性、愛と暴力、平等と差別が入り混じるこの世界は、あまりにも人間社会をリアルに反映しており、それが読者に強烈な印象を与えているのだと思います。
死亡キャラ一覧とその意義を振り返る
ビースターズには、物語の展開に大きな影響を与えた死亡キャラが複数登場し、その死には重要な意味が込められています。
この作品は、動物たちの擬人化を通して、社会の暴力性や差別構造、愛と本能のジレンマを描いています。そのため、キャラクターの死は単なる悲劇としてではなく、物語全体を前に進める装置として扱われています。
代表的な死亡キャラの一人が、冒頭で食い殺されたアルパカのテムです。彼の死は学園内に緊張をもたらし、物語全体の導入とレゴシの探偵的な行動の出発点になりました。食殺事件というショッキングな導入は、読者に一気に作品世界へ引き込む効果を持ちます。
次に重要なのが、物語終盤の鍵となるメロンです。彼は草食と肉食の混血として生まれ、差別と孤独に苦しんだ末に裏市を支配し、社会に対して破壊的な行動を取るようになります。
最終的に、ハルとの関係を通して「愛すること」と「食べること」の狭間で揺れ、死を選んだと考えられています。この死は、彼の苦悩を終わらせると同時に、裏市に変革をもたらす転機にもなったと読み解けます。
さらに一部ファンの間では、「本来は死亡していたが、物語が改変されたことで生存したキャラ」がいると考察されています。その一人が公安のヤフヤであり、彼は本来メロンに殺されるはずだったが、レゴシたちが世界を「変えた」ことにより生存ルートに切り替わったのではという説が語られています。
このように、死亡キャラの存在は単なる物語の演出ではなく、キャラクターたちの思想や社会構造、作者の問題提起そのものを内包しています。彼らの死を振り返ることで、ビースターズという物語が何を語ろうとしたのか、より深く理解することができるのです。
レゴシとハルの子供の描写がない理由とその意味
ビースターズの物語では、主人公レゴシとヒロイン・ハルの恋愛関係が中心に描かれているにもかかわらず、最終回までに二人の「子供」に関する描写が一切登場しません。これは、作者の意図による重要な選択だったと考えられます。
理由は、ビースターズという作品が単なるラブストーリーではなく、「異種族間の理解」と「共存の難しさ」という社会的テーマを扱っているからです。種族の違いを超えた恋愛は成立しても、それが出産や家庭という未来に直結するかは、現実以上にデリケートな問題となります。
たとえば、ハルは草食動物であるウサギ、レゴシは肉食であるオオカミという関係です。実際の自然界においてはあり得ない組み合わせであり、それゆえにこの恋愛関係自体が一種の「挑戦」であることが読者に示されています。
しかし、物語の最後に「子供が生まれた」という描写をしてしまえば、読者はその恋が「結果として成功した」と単純に受け取ってしまうかもしれません。
物語全体を通じてレゴシとハルの関係は、対立と理解、葛藤と妥協を繰り返しながら成長していく様子が描かれます。そこに「子供」という要素が加わると、リアルな現実感ではなく、「ファンタジー」や「ご都合主義」として見られる危険がありました。
また、作中には「肉食と草食が本能レベルで分かり合えない」という描写が何度も出てきます。そのため、「子供」という究極の融合を描かないことで、あえて両者の壁を残したまま終わらせることでテーマ性を際立たせたとも受け取れます。
レゴシとハルの未来は描かれないまま終わりますが、それは彼らの関係性が一つの「完成形」ではなく、「これからも続くプロセス」であることを示す演出だったのではないでしょうか。子供の描写がないことで、むしろ読者にその後の想像の余地を残し、物語を余韻あるものにしているのです。
最終回があっさりだった理由と読者の反応
ビースターズの最終回は、多くの読者にとって「あっさりしすぎた」と受け止められました。これは、物語のクライマックスにおける重要な要素が描かれなかったことが大きく影響しています。
その最大の理由は、物語の核心である「メロンとハルの関係性」や、「博愛の食肉」とされる象徴的エピソードが作中で一切描かれなかったことにあります。特に、第166話の「奇魂祭」で語られた、ハルがメロンに「食べてもいい」と告げた約束は、読者の中で重大な伏線として捉えられていました。
ところが、最終巻(22巻)では、その伏線が完全に無視されたかのように処理され、メロンとの対決もあっけなく終了します。読者が長らく待ち望んでいたメロンの心理やハルとのやり取りがすべて省略されていたため、急に打ち切られたような印象を与えたのです。
加えて、登場人物たちの今後がほとんど描かれず、結末として「世界が変わった」という抽象的な言葉でまとめられたことも、不満の一因となりました。「レゴシとルイが世界を変えた」と繰り返し語られるものの、それがどのような変化だったのか具体的には描かれず、読者にとって消化不良を残す終わり方だったのです。
こうした終わり方に対して、SNSやレビューサイト、5ちゃんねるのスレッドなどでは「風呂敷を畳みきれていない」「核心部を描いてない」「メロンが完全に空気になった」などの声が多く見られました。
中には、「本当は描くつもりだったが、ネットで展開が予想されたため作者があえて避けたのではないか」とする見方も出ています。これは作者・板垣巴留が「嫌いなものはインターネット」とコメントしたことと結び付けられて語られています。
結果として、最終回の印象は「唐突」かつ「未完成」に映り、物語に深く入り込んでいたファンほど衝撃を受けたようです。しかし、そうした終わり方があったからこそ、ビースターズは単なるエンタメ作品ではなく、読み手に問いを投げかける作品として記憶に残っているともいえるでしょう。
ビースターズの打ち切り理由とアニメ展開の関係|未回収の伏線に迫る
-
ビースターズ 打ち切り アニメはなぜ途中感があるのか?
-
ビースターズ レゴシ 死亡説の真相と結末の解釈
-
ビースターズ ジュノ 死亡の噂と未完のラブストーリー
-
ビースターズ 続編の可能性とファンが期待する未来
-
ビースターズ 作者・板垣巴留の創作スタンスとネットへの抵抗
-
ビースターズ ネタバレ全開で読み解く核心未描写の真意とは?
アニメはなぜ途中感があるのか?
ビースターズのアニメには「途中で終わってしまった」という印象が強く、打ち切りを疑う声が視聴者の間で多く上がっています。これは、最終シーズンであるアニメ第3期が物語の核心に触れず、決着が曖昧なまま完結したように見えるためです。
その理由は、原作の終盤に描かれるべき重要な要素、特に「メロンとハルの関係性」や「博愛の食肉」というテーマがアニメではまったく触れられなかったことにあります。原作を読んでいる視聴者ほど、核心部がすっぽり抜け落ちているように感じ、物語が未完のまま終了したような印象を持つのです。
具体的には、Netflixで配信されたアニメ版の最終話(ファイナルシーズン)では、メロンが大学の教壇に立つシーンで物語が締めくくられます。しかし、それまでの流れや対立構造が急に途切れたまま終わるため、物語上の大きな山場や感情のカタルシスを得られない視聴者が多くいました。
また、アニメ制作を手がけたスタジオ「オレンジ」は3DCG表現に高評価を得ている一方、シリーズ構成上、描写が削られたり改変されたりすることも少なくありませんでした。
こうした演出や構成の選択が、原作ファンから「駆け足すぎる」「雑なまとめ」と感じられ、途中感を助長したのです。
加えて、アニメ版では「ルイとレゴシが世界を変えた」と繰り返されるものの、それがどのような影響をもたらしたのか具体的に描かれず、視聴者にとっては物語の本質が理解しづらい構成となっていました。
視聴者の中には、打ち切りではなく「意図的に描かなかったのでは?」という意見もあり、真相は制作側のみが知るところですが、結果として「途中で終わったように感じた」とする感想が広く共有されたのは事実です。
アニメだけを見た人にとっては、完結というより「中断」に近い印象を残したシリーズとなりました。
レゴシ死亡説の真相と結末の解釈
ビースターズの完結後、一部の読者や視聴者の間で「レゴシは最終的に死亡したのでは?」という説が囁かれています。この死亡説は、明確な描写が存在しないにもかかわらず、終盤の曖昧な表現や象徴的な演出から浮上したものです。
このような疑問が生まれた背景には、レゴシのキャラクターが常に「肉食獣であることへの罪悪感」や「自己犠牲」に満ちた選択を繰り返してきたという点があります。
彼は草食動物を守るために社会から逸脱し、裏市で孤独に戦うような立場を取ってきました。そのため、最終的に自分の存在ごと消えるようなエンディングが用意されているのではないかと予想されたのです。
しかし、実際の物語ではレゴシの死を直接的に描いたシーンは存在しておらず、むしろ彼がメロンとの対決後も生存していることは作中の会話や演出から読み取ることができます。
特に、ルイとのやり取りや、ハルとの関係性が続いているような描写があるため、結末としては「レゴシは生きている」という解釈が自然です。
ではなぜ、死亡説が一定の支持を得ているのかというと、それは終盤の物語構成にあります。
ビースターズのラストは、あまりに多くのエピソードを省略してまとめられており、読者に対して余白や解釈の余地を与える構造となっています。その中で、「レゴシが自らの存在を消して世界を変えたのではないか」とする読者の想像が広がっていったのです。
さらに、「世界を変えた」という抽象的な表現の繰り返しが、「レゴシ自身が何か大きな犠牲を払った結果」と受け取られたことも要因のひとつです。
作中で語られる「世界が変わった」というフレーズは、裏市や社会構造の変化を意味しているものの、それが誰の犠牲によってもたらされたのかは明言されていません。その曖昧さが、死亡説の根拠となっているのです。
結果として、レゴシ死亡説は明示されていないものの、作品の象徴性やテーマ性を深読みするファンの間で広がった解釈の一つといえます。実際の描写では生き延びているものの、読者が感じた「彼が払った代償の大きさ」が、この説を支えているのです。
ジュノ死亡の噂と未完のラブストーリー
ビースターズの登場キャラクター・ジュノには、一部で「死亡したのではないか」という噂が存在しますが、実際にはそのような描写は作中にありません。それでも死亡説が語られる背景には、彼女のストーリーが完結せずに放置されたように感じられる展開があるからです。
ジュノは、主人公レゴシと同じオオカミで、彼に好意を抱いて積極的にアプローチしてきたキャラクターです。しかし、レゴシの心は終始ハルに向いており、ジュノの想いが報われることはありませんでした。にもかかわらず、ジュノの恋の結末は描かれないまま、物語は終盤に突入し、やがて彼女の登場すらなくなっていきます。
この「消え方」が、ジュノの「死亡説」を呼んでいる一因です。読者の中には、物語の中で何らかの事件に巻き込まれたのではないか、あるいは裏市の抗争などの影響で命を落としたのではないかという解釈をする人もいます。しかし、公式に死亡が示されたわけではありません。
また、ジュノとレゴシの関係は、異種間恋愛を主軸に置いたレゴシ×ハルの構図の裏で、「同種族恋愛がうまくいかない」というもう一つの現実を描いた対比でもありました。ジュノの一途さ、レゴシに寄り添おうとする誠実さは読者の心を打ちましたが、最終的に報われることはなく、彼女自身の未来も示されないまま作品は幕を閉じます。
つまり、ジュノの「死亡」という噂は、物語の中で彼女があまりにも静かに退場したために生まれたものであり、同時にそのラブストーリーが未完のまま終わったことによる余韻でもあるのです。読者にとって、彼女は「もっと幸せになってほしかった」と願わずにいられない存在として、強く印象に残っています。
続編の可能性とファンが期待する未来
ビースターズには続編の可能性があるのではないかと、今でも多くのファンが期待を寄せています。その理由は、物語の多くの伏線が未回収のままであり、核心部分が意図的に描かれなかったからです。
特に、「博愛の食肉」と呼ばれるテーマが本編で描かれずに終わったことは、ファンの間で最も大きな不満点とされています。ハルがメロンに「自分を食べてもいい」と言ったという重要な約束や、メロンの死の真相、ヤフヤの生死、そして裏市の変革の過程など、物語上で非常に重要なパートがすべて省略されています。
このような描かれなかったエピソードを補完する形で、続編やスピンオフが展開される可能性は十分にあります。作者の板垣巴留が、既に短編集『BEAST COMPLEX』で同一世界観の話を展開していることからも、世界観を広げる余地はまだまだ残されているといえるでしょう。
また、読者の間では「描かれなかった=描くつもりがあるのではないか」という声もあり、アニメ版において補完される可能性も含め、さまざまな期待が寄せられています。特に「メロンとハルの約束」や「世界が変わったという出来事」の真相を明らかにすることで、物語はより高い完成度に達する可能性があります。
現時点では公式に続編の発表はありませんが、作品自体が大きな反響を呼び、アニメもNetflixでグローバルに配信されたことから、商業的にも再び動き出す余地は残されていると見られています。
ファンとしては、「あの未完の物語がどのように補完されるのか」を期待せずにはいられません。ビースターズの世界は、終わったように見えて、実は始まりに過ぎなかったのかもしれないという想像が、続編を待つ根拠の一つになっているのです。
作者・板垣巴留の創作スタンスとネットへの抵抗
ビースターズの作者・板垣巴留は、創作において極めて個性的なスタンスを持っており、それは作品の展開や結末の描き方、さらにはインターネットへの姿勢にも色濃く表れています。
その最大の特徴は、「読者の予想やネット上の意見に影響されない」ことを強く意識した創作態度です。これは、連載終盤の内容において顕著でした。たとえば、作中で最も重要とされる「メロンとハルの約束」(いわゆる「博愛の食肉」)のエピソードが描かれなかったのは、ネット掲示板でその展開を予想されたからではないかという説があります。
実際、2020年31号の『週刊少年チャンピオン』の巻末コメントで板垣巴留は「最近の好きなものはお素麺、嫌いなものはインターネットです!」と明言しています。
この発言が掲載されたタイミングと、物語で重要エピソードがごっそりカットされた時期が一致していることから、読者の一部では「ネットでネタバレされることを嫌がって、あえて描かなかったのではないか」と推測されているのです。
このスタンスは、読者の反応やSNSの動向に寄り添う現代の漫画家像とは一線を画すものであり、むしろ作家自身の創作欲求と直感を最優先して作品を進めるタイプだといえます。
たとえば、板垣氏はTwitterでも独自の価値観を披露しており、不在票を放置していた過去の自分と向き合って生き方を変えたという投稿なども話題になりました。
このようなエピソードから見えてくるのは、「物語は自分のタイミングで、思うように描きたい」という作者の強い信念です。読者に迎合せず、自分が納得できる形で完結させることを重視したからこそ、ビースターズは多くの人にとって「予想外」の展開になったのかもしれません。
ネットや外部の声に過剰に影響されることなく、己の表現を貫く──それが板垣巴留の創作スタンスであり、ビースターズという作品が唯一無二の存在となった理由でもあるのです。
ネタバレ全開で読み解く核心未描写の真意とは?
ビースターズという物語には、最後まで語られなかった「核心の未描写」が存在し、その真意を読み解くことで作品全体の構造がより明確になります。
とりわけ、メロンとハルの関係性、そして「博愛の食肉」というテーマは、物語の要でありながら本編で描かれなかったため、大きな波紋を呼びました。
物語のクライマックスであるはずの「メロンがハルを食べるという約束」──この重要な展開は、第166話の「奇魂祭」で言及されたのを最後に、以後一切触れられなくなります。なぜこんなにも重要なパートがスルーされたのか。
多くの読者が疑問に感じましたが、それはおそらく、作者が「愛と食肉の融合」という究極のテーマを、あえて描かないことで逆に強調したからだと考えられます。
このテーマは、『BEAST COMPLEX』に収録された短編でも既に扱われており、「愛する相手を自らの意志で食べさせる」という異種間の究極的な絆として描かれています。
レゴシがルイの足を食べたエピソードも同様の文脈にあり、「友情の食肉」、そしてメロンとハルの関係が描かれていれば「博愛の食肉」になったはずでした。
メロンは、差別も愛も嫌う中立的な獣であり、自分が混血であることを理由に虐げられる世界に失望していました。
そんな彼が、初めて出会った「普通に接してくれる」存在がハルだったというのは、メロンのキャラクター構造の核心を突いています。だからこそ、彼はハルに恋をし、結果として彼女を「食べたい」と思ってしまうのです。
物語の中では描かれませんが、ハルは再び「食べられてもいいかも」という気持ちになったことで、メロンとの約束を実行しようとします。しかし、メロンはその瞬間に「食べてしまったらハルが消える」と気づき、最終的に自ら命を絶つ決断をしたと解釈されています。
ではなぜこの一連の展開が描かれなかったのか。それは「描くことで物語の重心がレゴシからメロンに移ってしまう」ことを避けたかったから、あるいは「ネットで先読みされたくなかったから」ともいわれています。実際にネット掲示板にこの展開を先に書いた読者がいたこと、そしてそれ以降にこの話が消えたことは、偶然とも言い切れません。
最終的に、ビースターズの本当の結末とは「メロンが死んだ世界」ではなく、「メロンとハルの物語がなかったことにされた世界」だったのかもしれません。そしてその決断を下したのは、レゴシとルイの二人であり、「世界を変えた」という謎めいたセリフの真意は、そこで起きた物語の改変を示唆していたとも解釈できます。
つまり、核心の未描写とは、存在しなかったのではなく、意図的に“描かれなかった”ものなのです。その裏に隠された構造やテーマを読み解くことが、ビースターズを真に理解するカギとなるのです。
ビースターズの打ち切り理由を巡る全体像まとめ
-
「博愛の食肉」が未描写だったことが打ち切りと誤解された最大の要因。
-
メロンとハルの約束が作中で描かれず、物語の核心が不在となった。
-
作者・板垣巴留がネット予想を嫌い、意図的に展開をカットしたとの見方がある。
-
メロンの死の描写がなく、読者に考察を委ねる構成が多くの謎を生んだ。
-
世界観のリアルさとキャラの異種恋愛が「気持ち悪い」と感じる読者を生んだ。
-
レゴシとハルに子供がいない描写は、異種間の現実を象徴する意図とされる。
-
最終回が抽象的で、伏線未回収が多く、打ち切り印象を強めた。
-
アニメ版は核心を描かず「途中で終わった感」が強い内容となっていた。
-
メロンの存在感が終盤で希薄化し、物語の重心が見えにくくなった。
-
ジュノの恋愛未完や突然の退場が「死亡説」まで呼び起こしている。
-
裏市やヤフヤの描写不足も、物語の重要要素の未解決感を生んだ。
-
「世界を変えた」という抽象表現が多くの誤解や憶測を呼んだ。
-
作者が描きたかったテーマがネットで予想されたことによる演出の自粛が噂された。
-
「愛の食肉」「友情の食肉」に続く「博愛の食肉」が描かれなかったことが象徴的。
-
続編やスピンオフの可能性が語られるほど、多くの謎が未解決のまま残った。
-
レゴシ死亡説が読者の間で生まれたのは、終盤の曖昧な演出の影響による。
-
読者の推測が展開に影響したとされる父・板垣恵介との共通点も話題に。
-
SNSや5ちゃんねるでは、核心を避けた展開に不満の声が多数見られた。
-
結末の抽象性がビースターズをエンタメ以上の哲学的作品にしたとも評価される。


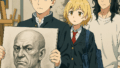
コメント